
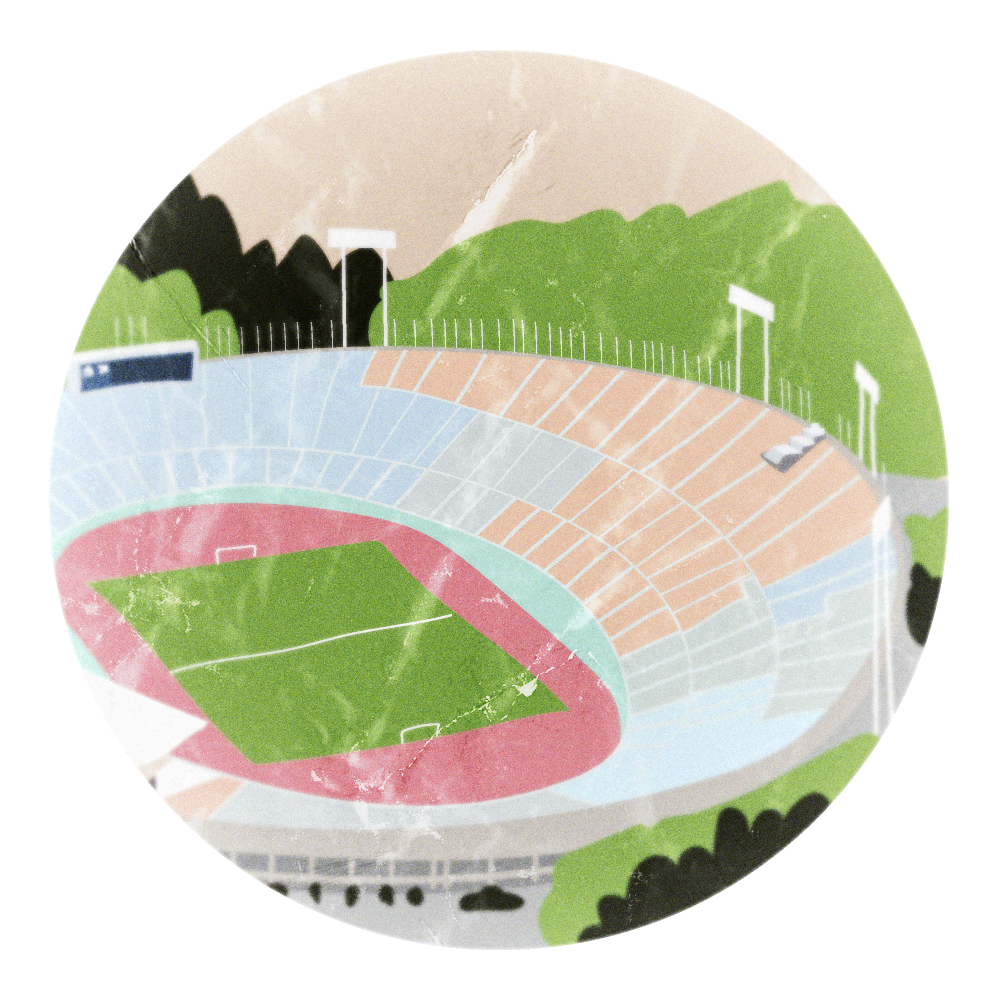
#29
二〇一四年、国立競技場
At National Stadium in 2014
読了時間:約10〜15分
代々木の駅を降りて明治通り沿いに原宿方面へと進み、左手の路地の奥に折れた雑居ビルの二階のカフェが、指定された場所だった。
約束の十分前にその店に入ると、奥の席にいた女が立ち上がり、こちらに向けて小さく頭を下げた。
てっきり、四十代後半のいかつい顔の女が眉間にしわを寄せてやって来ると思っていた。でもそこで私を待ち構えていたのは、グレーのパーカーを着た、背の低い、猫のような顔をした、まだ学生みたいな若い女だった。
「えっと……」
いざ対面してみると、何と切り出してよいかわからない。まごついていると、彼女は私の恋人の名前をフルネームで口にし、の、娘です、と付け加えた。
◇
「母が怖じ気づいちゃったんで、かわりに私が来ました」
彼女は挨拶の代わりに言った。そしてまん丸の瞳で私の顔をじっと見つめると、
「きれいな人でよかった」
と口の端を少し持ち上げ、席に着いた。私は返す言葉を見つけられず、店員が水を持ってやってくるタイミングでようやく椅子を引いた。メニューは開かずにコーヒーを注文した。
「私は紅茶で」
目の前の彼女が言い、それはコーヒーが飲めない父親と、ああ、まったく同じであるなと妙に納得したけれど、私は黙っていた。
「おいくつですか?」
そう聞かれて、三十二です、と私は答えた。
「イヌですね」
さっそく罵倒されたかと思った。盛りのついた犬ですか、三十二にもなって。まわりに独身の三十代の男なんていくらでもいるでしょう。よりによってうちの父を ― そんなふうに責められるかと身構えていると、
「私もイヌなんで」
彼女が言い、干支の話だとわかった。
どうやら彼女は二十歳らしい。
◇
恋人 ― といっても、達彦さんと「恋人同士」という意識は、正直なところ私にはあまりない。達彦さんは前の職場の人だった。今は、私の ― この言葉もしっくりくるものではないけれど ― 不倫相手だ。
私は、目の前の達彦さんの娘と同じ年の頃、短大を卒業して事務機器を扱うメーカーの子会社に就職し、その会社を一年で辞めている。
そのとき、職場にうまく適応できないでいた私のことをずっと気にかけてくれたのが、同じフロアで働いていた達彦さんだった。
「社会人っていうけど、社会はひとつじゃないから。いろんな社会があって、みんなそれぞれ、自分に合う社会で社会人になればいいと思うよ」
ときどき、そんなアドバイスで達彦さんは私の重たく凝り固まった心をほぐしてくれた。営業の主任で、サッカーが好きで、日本代表の大きな試合があるときは会社の人に声をかけてみんなでスポーツバーに飲みに行くような、明るくて元気な、いかにも社会に適応しているタイプの人だった。
会社を辞める二ヶ月前、なんだか様子が心配だからと、達彦さんは私を飲みに誘ってくれた ― 当時はまだ、主任、と呼んでいた。
仕事も、人間関係も、何もかも上手くいかずに少し鬱状態になっていた私のことを気遣って、
「人は無理をするのがいちばんよくないよ。今の時代はさ、ばりばり働くことが当たり前みたいになっているけど、そんなことはないからね。疲れたら休む、そのことの方が当たり前なんだよ」
と言ってくれた。その言葉のおかげで、私は会社を辞める決心がついた。
ちゃんとお礼を言わなくちゃと思いつつ、言えないまま私はその会社を去った。
◇
達彦さんと偶然再会したのは、それからだいぶ経ってからのこと。仕事帰りの新宿の駅だった。
「那須ちゃん!」
雑踏の中で背後から呼び止められ、振り向くと、懐かしい顔があった。
「主任!」
「うわー、久しぶりだね。改札通るとき見かけて、思わず尾行して声かけちゃったよ。ずっと気になってたからさあ、いやあ、よかった会えて。元気? あ、仕事帰り? もし時間あったらそのへんでご飯食べない?」
西口の居酒屋でふたりで刺身を食べた。
「懐かしいね、えーっと那須ちゃんと一緒に仕事してたのは、ワールドカップが南アフリカの前……いや、ドイツの前か。ってことは」
「もう十年くらい前ですね」
「だよね」
「相変わらずサッカー好きなんですね」
「いや、最近はあんま見てないけどね」
私は当時言いそびれたお礼をちゃんと言って、
「主任のおかげで、私、立ち直れました。今は元気にやっています」
と、あれからしばらく仕事を休んで、心療内科に通い、知り合いのやっている服屋でバイトをしながら少しずつ社会に慣れていき、それから派遣事務を経て今は普通に会社員をしている、というこれまでの流れを伝えた。
「で、どんな仕事を?」
「アパレルのネット通販の会社でデザインの仕事をしています。デザインっていっても、お洒落な感じじゃなくて、ただのオペレーター業務ですけど。前の会社辞めてから、少し休んで、デザインのスクールに通ったんですよ。そこでソフトの使い方とか習って、それでそっち方面でいくつか仕事して、今の会社に落ち着きました。アパレルはバイトの経験があったんで、馴染みやすいかなと思って」
達彦さんは終始にこやかに、楽しそうに私の話を聞いてくれた。
終電間際まで飲んで、その夜は新宿駅の改札で別れた。いやー、那須ちゃんが元気でよかった、また飲もうよ、と言われて、連絡先を交換した。
そしてその二ヶ月後、私は達彦さんと再び会って、ご飯を食べて、お酒を飲んで、酔いつぶれた達彦さんを介抱するためにホテルに入って、そして寝た。
最初からそのつもりで会ったわけではなかった。その日の達彦さんは、仕事で何か問題を抱えていたのか、なんだかひどく疲れた様子で、というか憔悴しきっていて、私は、今度は自分が彼を励ます番だ、という気持ちになった。でも私にできることなんて何もなくて、そばにいることくらいだった。
彼に奥さんもお子さんもいることは知っていた。一回だけのつもりだった。
◇
それから、達彦さんとときどき会うようになった。
連絡は不定期で、いつも達彦さんの方からメッセージが届いた。急にお昼に連絡が来てその日の夜に会うこともあれば、一週間以上前からこの曜日のこの時間に会おうと誘われることもあった。
ご飯を食べたりお酒を飲んだりがほとんどだったけれど、映画館やゲームセンターやボーリング場に行ったこともあった。そしてだいたい、最後はどこかのホテルに入った。
付き合っている、という感じではなかった。私には恋人がいなかったけれど、そもそも彼の方に家庭があったし、どうせそのうち終わるのだから、と思っていた。
そんな関係で一年が経ち、二年が経ち、三年が経ち ― いつでも別れられると思っていたからこそ、逆に、別れるタイミングがどこにもなかった。
何の前触れもなく、会社のメールアドレスに達彦さんの奥さんからのメールが届いたのが、一昨日の夕方のことだ。
私の都合などお構いなしに、約束の時間と場所を指定され、《女同士で、少し、お話をしましょう》とあった。
◇
「ついでにちょっと軽食とっていいですか? 実はお昼、食べ損ねちゃって」
紅茶を頼んだ後で、そう言ってメニューを開いた彼女は、今、私の目の前で美味しそうにロコモコを食べている。
その様子を眺めながら、達彦さんとはこれで終わりだな、と私は思った。
もう会わないでくれと約束をさせられるのは分かっている。奥さんと闘う気なんてないし、もちろん、娘さんと言い争うのも本意ではない。
ただ現実的な話、慰謝料を請求されたらどうしようという心配だけがあった。独身とはいえ薄給の身で貯金はあまりない。親に頼るのも、事情が事情なだけにできれば避けたい。せっかく東京に出してやったのにそんなことなら今すぐ田舎に帰って来い、と父に怒鳴られるのは目に見えている。
◇
「あの、会うならバレないように会ってもらえませんか?」
セットについてきたコンソメスープを飲み干してから、彼女は言った。
「え?」
「母には、『もう二度と会わないと約束させた』って言います。だから、これからはもう絶対にバレないように。それが私のお願いです」
私が答えられずにいると、
「うちの親、夫婦仲がすごく悪いんですよ」
と、彼女は身を乗り出してきた。まるで友達に秘密を打ち明けるときみたいに。
「だから、うちのお父さんが那須さんみたいなきれいで頭のよさそうな人と出会ったら、よろめいちゃうのは分かるっていうか、まあ当然だろうなって思うんですよね。私としてはむしろ、お父さんよかったね、ってくらいな気持ちなんですよ。てか、父を好きになってくれてありがとうございます。でも、そういうこと言うとうちの母、キレてやばいことになるんで。とりあえず『もう金輪際会わないことにした』ってことにしてください。次、もしバレたら百パー慰謝料ですから。気をつけてくださいね。うちの母、ちょっとここ、やばいんで。話通じる人じゃないですから」
そう言って、彼女は人差し指で自分のこめかみに触れた。思わぬ展開だった。
「那須さん、これからって時間ありますか?」
「え、あ、はい」
「じゃあちょっと、付き合って欲しいところがあるんですけど」
◇
彼女に連れて行かれた先は、国立競技場だった。神宮外苑の緑が生い茂る中、重厚なコンクリートのかたまりがそびえ立っていた。ゲートのそばで見上げて、まるで巨大な古墳のようだ、と私は思った。古墳を見たことは一度もないけれど。
「那須さんてサッカー、見たことあります?」
「いえ、ないです」
ちょうどJリーグの試合を開催しているらしく、千駄ヶ谷の駅前あたりからサッカーのユニフォームを着たサポーターと何度もすれ違った。
「敬語じゃなくていいですよ。那須さんよりひとまわりも年下なんで、私」
「あ、はい」
彼女はチケット売場を見つけると、そこで自由席券を二枚を買った。
「お金、私が払います。あ、払うよ」
「別にいいですよ」
「でもほら、さすがにおごってもらうのも変だし。私、ひとまわり上だし」
「じゃあ、私への慰謝料ってことで。お願いします」
そう言って笑う彼女の表情に、父親の不倫相手に対する敵意や侮蔑のようなものはまったく感じられなかった。
「サッカーよく見に来るの?」
「昔はよく父と兄に連れられて来たんですけど、最近はもう全然。久しぶりです。さっきのお店に行く途中でこのへん歩いてたらサポーターの人がいっぱいいて、久しぶりに帰りにサッカーでも見ようかなーって思ったんですよ。誘うつもりはなかったんですけど、なんか、会ったら一緒に見たくなっちゃいました」
◇
広々としたスタンドに、お客さんの姿はまばらだった。ゴール裏の席にはサポーターのかたまりが陣取っていたけれど、それ以外はどこでも自由に座れるような感じだった。
「サッカーは、バックスタンド中央の上から見下ろすのがいちばんだって、お父さんよく言ってたんですよね。もうちょっと上、行きましょうか」
そう言いながら階段を上がる彼女についていく。視線を上げると、彼女のスカートの奥が見えそうだった。
スタンドのいちばん上のエリアの誰もいない列の端に彼女が腰を下ろし、私もその隣に腰掛けた。
どことどこの試合だったか、どちらが勝ったのかは覚えてはいない。ゴールが決まったのか、そうでなかったのかも。
覚えているのは、サッカーの試合を眺めながら聞いた、彼女の話だけだ。
◇
今は暖かいからいいですけど、春先とか秋の終わりとか、天皇杯の時期とかって、サッカー場、まじで寒いんですよ。もう足首まで届くくらいのメンズのぶかぶかのベンチコートとかダウンとか着て見てましたね。
うちのお兄ちゃん、小学校のときからずっとサッカーやってて、高校でもいいとこ行ったんです。全国には出られなかったけど、トレセンとかに選ばれたこともあって。うちの父、サッカー好きなんで、よく父とお兄ちゃんと私でJリーグとか代表戦とか、見に行って。
その兄がね、死んじゃったんです。
事故で。大学生のとき。
みんなショックで、もうどうしていいか、私なんかもいまだによく分からないんですけど、父はもうほんとに落ち込んで。ずっと、お兄ちゃんに期待してたんですよ。
大学受験のときも、もしサッカー留学したけりゃブラジルでもヨーロッパでも行ってこい、とことんまで頑張ってみろとか言って資料まで取り寄せて。でも大学のスカウトの人が来たら、それはそれで喜んじゃって、はしゃいじゃって。
兄が亡くなってから少しして、父が突然いなくなったことがあったんです。何日も家に帰ってこなくて、心配で母と探しに行って、警察にも電話して。そしたら、警察から保護したって連絡があって。この、国立競技場のスタンドの、あの向こうの電光掲示板の下のあたりの席でうずくまって泣いていたんです。試合のある日で、試合が終わってもずっとそこにいるから、変な人がいるって警備員呼ばれて、それで警察に連絡が入って。
兄がずっと言ってたんですよ。国立のピッチに立ちたいって。知ってます? 高校サッカーって、全国大会の決勝とかここでやるんですよ。高校野球は甲子園じゃないですか、高校サッカーは国立なんですよ。聖地、みたいな。兄はここでプレーできなかったんですけど、でもいつかプロになってここでサッカーするのが夢だったんですよね。
うちのお父さん、弱い人なんですよ。私も、母もそうですけど、父は特別、兄のことが大好きだったんです。
兄のこと、知らなかったですか? 全然聞いてない? そっか、言えなかったんですね。那須さんに言えない気持ちもちょっと分かるっていうか、きっと言ったら、もう那須さんから離れられなくなっちゃうって思っているのかもしれないです、うちのお父さん。
実は私もね、今付き合ってる彼氏が、奥さんいる人なんですよ。そう、同じで。これからどうしよっかなあ、って考えるんだけど、早めにフェードアウトしなきゃって思うんだけど、なんか、どうにもできなくて。できないですよね。向こうの家族にバレて慰謝料払えとか言われてもお金ないし、とか思うんだけど、なんか、じゃあすぐ別れられるかっていうとそれはそれで無理って感じだし。淋しいし。
あの、うちのお父さん、たぶん那須さんが生き甲斐なんですよ、今。きっと。だから、私がこんなこと言うのは変ですけど、できたら捨てないであげてください。兄のこと、知っておいてあげてください。もし父が自分から話したら、聞いてあげてください。お父さんのこと、どうかお願いします。
知ってます? この国立競技場、もうすぐ壊されるんですよ。試合やるの今年いっぱいまでなんだって。オリンピック、東京に決まったじゃないですか。新しいスタジアムになるんです。この国立、なくなっちゃうんですよ。
世の中って、ずっと同じままみたいに思ってるけど、変わるんですよね。変わるんですよ。変わらないで、っていくら思っても、ずっとそのままじゃいられないんです。
でも私、この国立でサッカー見たこと、兄と父と一緒に通ったこと、今日、那須さんとここにいること、兄の話をしたこと、みんな忘れないです。いつか死んでも、きっと忘れないです。
◇
試合が終わってからだと道も電車も混むから、と彼女が言うので、私たちは試合が終わる少し前にスタンドを後にした。
外苑の木々の若葉の匂いの中を私たちは並んで歩き、そして千駄ヶ谷の駅前で別れた。
約束の場所にたどり着く前は、いろいろなことを覚悟していた。不倫の代償 ― そんな言葉が頭の中に常にあって、そのせいで人生が大きく変わってしまうかもしれないと思っていた。多額の慰謝料をどこかから借金しないといけない。会社を辞めなくちゃいけないかもしれない。いよいよ実家に引っ込むことになるかもしれない。
でも、どうやら何も変わらない。むしろ許された。それらの心配からはひとまず解放された。なのに、身体はなんだか鉛のように重かった。
改札の向こうに消えていく彼女の後ろ姿を見送ってから、私は来た道を振り返った。
何年か後に、この視線の先に、新しい国立競技場が誕生する。そこでオリンピックが開かれる。華々しく、賑やかに。世界中からたくさんの人が来て、日本中、その話でもちきりになる。本当だろうか。本当に、そんな未来があるのだろうか。
そのとき、私は誰と一緒にオリンピックを見るのだろう。
達彦さんであってほしい、と思うと同時に、それが達彦さんではない予感もする。
■
FOOTBALL SHORT NOVELS COLLECTION :
FOOTBALL AND LOVE SONG
Written by Masashi Fujita


© 2019. MASASHI FUJITA All Rights Reserved.
